社会保険
大きな意味で社会保険と言ったときに、社会保険と労働保険に分けられます。
社会保険 労働保険 労災(労働者災害補償保険)
雇用保険
社会保険 厚生年金保険
健康保険
今日は、社会保険(厚生年金保険・健康保険)について説明します。
社会保険は、厚生年金保険と健康保険があります。
厚生年金保険とは、会社などで働く人たちが年をとって働けなくなったとき、病気やけがが原因で障害の状態になったとき、不幸にして亡くなったりしたときに、年金や一時金を支給して働く人たちやその家族の生活の安定を図る制度です。
次に、健康保険とは、業務外の病気やけがに対して療養の給付や生活費の補償、また、出産や死亡に対しても補償が行われます。
出産育児一時金、家族出産育児一時金、
出産手当金
は健康保険からの支給となります。
会社の形態により、社会保険に加入しなければならない場合と社会保険に加入しなくても良い場合があるのですが、
会社がもし社会保険に加入していない場合、
従業員さんは、
厚生年金保険の代わりに国民年金に、
健康保険の代わりに国民健康保険に
加入することになります。

社会保険 労働保険 労災(労働者災害補償保険)
雇用保険
社会保険 厚生年金保険
健康保険
今日は、社会保険(厚生年金保険・健康保険)について説明します。
社会保険は、厚生年金保険と健康保険があります。
厚生年金保険とは、会社などで働く人たちが年をとって働けなくなったとき、病気やけがが原因で障害の状態になったとき、不幸にして亡くなったりしたときに、年金や一時金を支給して働く人たちやその家族の生活の安定を図る制度です。
次に、健康保険とは、業務外の病気やけがに対して療養の給付や生活費の補償、また、出産や死亡に対しても補償が行われます。
出産育児一時金、家族出産育児一時金、
出産手当金
は健康保険からの支給となります。
会社の形態により、社会保険に加入しなければならない場合と社会保険に加入しなくても良い場合があるのですが、
会社がもし社会保険に加入していない場合、
従業員さんは、
厚生年金保険の代わりに国民年金に、
健康保険の代わりに国民健康保険に
加入することになります。

Posted by 青い夜 2006年11月29日09:03│Comments(0)
│社会保険
労働保険
大きな意味で社会保険と言ったときに、社会保険と労働保険に分けられます。
社会保険 労働保険 労災(労働者災害補償保険)
雇用保険
社会保険 厚生年金保険
健康保険
今日は、労働保険について説明します。
労働保険は、労災と雇用保険があります。
労災とは、仕事中のけがや、仕事を原因とした病気の補償をするものです。
通勤時のけがについても、労災が適用されます。
労災については、育児休業とはそれほど密接に関わりがありません。
次は雇用保険です。
雇用保険とは、労働者が失業に陥ったときに、再就職まで生活を安定させるものです。
また、失業を防ぐためのものでもあります。
“育児休業給付金”は、この、雇用保険から支給されています。
育児休業給付金がもしなければ、育児休業中に収入がなくなってしまい、
会社を辞めてしまう場合もあるのですね。
ですから、失業を防ぐため・雇用を継続するために、育児休業給付金が雇用保険から支給されています。
また、育児休業期間中については育児休業基本給付金が、支給され、
育児休業終了後6ヶ月経過後にも育児休業者職場復帰給付金が支給されますが、
これは、育児休業を終了すると、会社を辞めてしまう人が多かったために、「6ヵ月後」に支給されるようになっています。

社会保険 労働保険 労災(労働者災害補償保険)
雇用保険
社会保険 厚生年金保険
健康保険
今日は、労働保険について説明します。
労働保険は、労災と雇用保険があります。
労災とは、仕事中のけがや、仕事を原因とした病気の補償をするものです。
通勤時のけがについても、労災が適用されます。
労災については、育児休業とはそれほど密接に関わりがありません。
次は雇用保険です。
雇用保険とは、労働者が失業に陥ったときに、再就職まで生活を安定させるものです。
また、失業を防ぐためのものでもあります。
“育児休業給付金”は、この、雇用保険から支給されています。
育児休業給付金がもしなければ、育児休業中に収入がなくなってしまい、
会社を辞めてしまう場合もあるのですね。
ですから、失業を防ぐため・雇用を継続するために、育児休業給付金が雇用保険から支給されています。
また、育児休業期間中については育児休業基本給付金が、支給され、
育児休業終了後6ヶ月経過後にも育児休業者職場復帰給付金が支給されますが、
これは、育児休業を終了すると、会社を辞めてしまう人が多かったために、「6ヵ月後」に支給されるようになっています。

Posted by 青い夜 2006年11月27日11:37│Comments(0)
│社会保険
社会保険の説明
今日は、「社会保険」の説明をします。
(もちろん、育児休業とも密接に関係しています)
ひとくちで「社会保険」と言っても、その場面により、意味合いが変わってしまいます。
ここでは、会社で入る社会保険についての説明になります。
大きな意味としての「社会保険」とは、
厚生年金保険
健康保険
労災(労働者災害補償保険)
雇用保険
の4つとなります。
このうち、
厚生年金保険
健康保険
の2つを社会保険、
労災
雇用保険
の2つを労働保険
と呼びます。
つまり、ただ「社会保険」と言った場合には、
全体として言っているのか、
厚生年金保険・健康保険のことを言っているのか
によって、大きく意味合いが異なってしまいます。
どう使い分けるかというと、
世間一般的に「社会保険」というと、全体のことを指します。
具体的な話になると、厚生年金保険・健康保険のことを指します。
ただ、世間一般ではっきりとわけて使っているわけではないので
(もちろん私たち社会保険労務士が発言するときには区別しますが)
注意が必要です。
私自身も、相談を受けるときには、ここは最初に注意すべき点です。
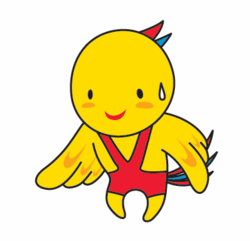
(もちろん、育児休業とも密接に関係しています)
ひとくちで「社会保険」と言っても、その場面により、意味合いが変わってしまいます。
ここでは、会社で入る社会保険についての説明になります。
大きな意味としての「社会保険」とは、
厚生年金保険
健康保険
労災(労働者災害補償保険)
雇用保険
の4つとなります。
このうち、
厚生年金保険
健康保険
の2つを社会保険、
労災
雇用保険
の2つを労働保険
と呼びます。
つまり、ただ「社会保険」と言った場合には、
全体として言っているのか、
厚生年金保険・健康保険のことを言っているのか
によって、大きく意味合いが異なってしまいます。
どう使い分けるかというと、
世間一般的に「社会保険」というと、全体のことを指します。
具体的な話になると、厚生年金保険・健康保険のことを指します。
ただ、世間一般ではっきりとわけて使っているわけではないので
(もちろん私たち社会保険労務士が発言するときには区別しますが)
注意が必要です。
私自身も、相談を受けるときには、ここは最初に注意すべき点です。
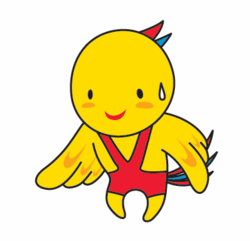
Posted by 青い夜 2006年11月20日19:16│Comments(0)
│社会保険
制度のまとめ
今日は、これまでお話してきた育児休業の制度のまとめです。
育児休業の主な制度として、5つの制度がありました。
・育児休業
・勤務時間短縮等の措置
・時間外労働の制限
・深夜業の制限
・子の看護休暇
ひとつひとつ概要のおさらいをします。
育児休業
制度概要
1歳(一定の場合は1歳半)までの子を養育する親が休業を取得する制度。
適用除外労働者
・日々雇用される者
・期間雇用者(一定の要件を満たした期間雇用者は対象となる)
・労使協定により除外される以下の者
①勤続1年未満の者
②労働者の配偶者が次の(イ)~(ニ)の要件をすべて満たす場合
(イ)職業に就いていない、または週の所定労働日数が2日以下
(ロ)負傷、疾病または精神上・身体上の障害により、子を養育することが困難な状態でない
(ハ)産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内でないか、産後8週間を経過している
(ニ)子と同居している
③休業の申出のあった日から1年以内に雇用関係が終了する労働者
④週の所定労働日数が2日以下の労働者
⑤内縁の妻(夫)等で休業申出にかかる子と法律上の親子関係がある者が前記(イ)~(ニ)の要件をすべてみたしている労働者
勤務時間短縮等の措置
制度概要
3歳までの子を養育する労働者が次の6つの制度のいずれか、もしくは2つ以上の制度を利用できる。
①短時間勤務制度
②フレックスタイム制
③始業・就業時刻の繰上げ・繰下げ
④所定外労働をさせない制度
⑤託児施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与
⑥1歳(育児休業を延長できる場合は1歳6か月)以上の子を養育する労働者については、育児休業の制度に準ずる措置でも講じても良い
適用除外労働者
・日々雇用される者
・労使協定により除外される以下の者
①勤続1年未満の者
②労働者の配偶者が次の(イ)~(ニ)の要件をすべて満たす場合
(イ)職業に就いていない、または週の所定労働日数が2日以下
(ロ)負傷、疾病または精神上・身体上の障害により、子を養育することが困難な状態でない
(ハ)産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内でないか、産後8週間を経過している
(ニ)子と同居している
③週の所定労働日数が2日以下の労働者
④内縁の妻(夫)等で休業申出にかかる子と法律上の親子関係がある者が前記(イ)~(ニ)の要件をすべてみたしている労働者
時間外労働の制限
制度概要
小学校の始期に達するまでの子を養育する労働者が請求したときに、
事業の正常な運営を妨げる場合を除き、
三六協定により労働時間を延長する場合であっても、
1ヶ月24時間、1年150時間を超えて労働時間を延長させないという制度
適用除外労働者
①日々雇用される者
②勤続1年未満の者
③労働者の配偶者が次の(イ)~(ニ)の要件をすべて満たす場合
(イ)職業に就いていない、または週の所定労働日数が2日以下
(ロ)負傷、疾病または精神上・身体上の障害により、子を養育することが困難な状態でない
(ハ)産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内でないか、産後8週間を経過している
(ニ)子と同居している
④週の所定労働日数が2日以下の労働者
⑤内縁の妻(夫)等で休業申出にかかる子と法律上の親子関係がある者が前記(イ)~(ニ)の要件をすべてみたしている労働者
深夜業の制限
制度概要
小学校の始期に達するまでの子を養育する労働者が請求したときに、
事業の正常な運営を妨げる場合を除き、
午後10時から午前5時までの間に労働を免除される制度
適用除外労働者
①日々雇用される者
②勤続1年未満の者
③請求にかかる家族の16歳以上の同居の家族が次の(イ)~(ハ)の要件をすべて満たす場合
(イ)深夜において就業していない者(1ヶ月について深夜における就業が3日以下の者を含む)
(ロ)負傷、疾病または精神上・身体上の障害により、保育が困難な状態でない
(ハ)産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内でないか、産後8週間を経過している
④週の所定労働日数が2日以下の労働者
⑤所定労働時間の全部が深夜にある労働者
子の看護休暇
制度概要
小学校就学前の子を養育する労働者が、申し出ることにより、1年に5日まで、病気・けがをした子の看護のために、休暇を取得することができる制度
適用除外労働者
・日々雇用される者
・労使協定により除外される以下の者
①入社6ヶ月未満の労働者
②1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
今日は、まとめですが、
これを見てもなかなかややこしくて理解できないかもしれませんね。
とりあえずは5つの制度があるということを理解していただければ、それで十分です。

育児休業の主な制度として、5つの制度がありました。
・育児休業
・勤務時間短縮等の措置
・時間外労働の制限
・深夜業の制限
・子の看護休暇
ひとつひとつ概要のおさらいをします。
育児休業
制度概要
1歳(一定の場合は1歳半)までの子を養育する親が休業を取得する制度。
適用除外労働者
・日々雇用される者
・期間雇用者(一定の要件を満たした期間雇用者は対象となる)
・労使協定により除外される以下の者
①勤続1年未満の者
②労働者の配偶者が次の(イ)~(ニ)の要件をすべて満たす場合
(イ)職業に就いていない、または週の所定労働日数が2日以下
(ロ)負傷、疾病または精神上・身体上の障害により、子を養育することが困難な状態でない
(ハ)産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内でないか、産後8週間を経過している
(ニ)子と同居している
③休業の申出のあった日から1年以内に雇用関係が終了する労働者
④週の所定労働日数が2日以下の労働者
⑤内縁の妻(夫)等で休業申出にかかる子と法律上の親子関係がある者が前記(イ)~(ニ)の要件をすべてみたしている労働者
勤務時間短縮等の措置
制度概要
3歳までの子を養育する労働者が次の6つの制度のいずれか、もしくは2つ以上の制度を利用できる。
①短時間勤務制度
②フレックスタイム制
③始業・就業時刻の繰上げ・繰下げ
④所定外労働をさせない制度
⑤託児施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与
⑥1歳(育児休業を延長できる場合は1歳6か月)以上の子を養育する労働者については、育児休業の制度に準ずる措置でも講じても良い
適用除外労働者
・日々雇用される者
・労使協定により除外される以下の者
①勤続1年未満の者
②労働者の配偶者が次の(イ)~(ニ)の要件をすべて満たす場合
(イ)職業に就いていない、または週の所定労働日数が2日以下
(ロ)負傷、疾病または精神上・身体上の障害により、子を養育することが困難な状態でない
(ハ)産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内でないか、産後8週間を経過している
(ニ)子と同居している
③週の所定労働日数が2日以下の労働者
④内縁の妻(夫)等で休業申出にかかる子と法律上の親子関係がある者が前記(イ)~(ニ)の要件をすべてみたしている労働者
時間外労働の制限
制度概要
小学校の始期に達するまでの子を養育する労働者が請求したときに、
事業の正常な運営を妨げる場合を除き、
三六協定により労働時間を延長する場合であっても、
1ヶ月24時間、1年150時間を超えて労働時間を延長させないという制度
適用除外労働者
①日々雇用される者
②勤続1年未満の者
③労働者の配偶者が次の(イ)~(ニ)の要件をすべて満たす場合
(イ)職業に就いていない、または週の所定労働日数が2日以下
(ロ)負傷、疾病または精神上・身体上の障害により、子を養育することが困難な状態でない
(ハ)産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内でないか、産後8週間を経過している
(ニ)子と同居している
④週の所定労働日数が2日以下の労働者
⑤内縁の妻(夫)等で休業申出にかかる子と法律上の親子関係がある者が前記(イ)~(ニ)の要件をすべてみたしている労働者
深夜業の制限
制度概要
小学校の始期に達するまでの子を養育する労働者が請求したときに、
事業の正常な運営を妨げる場合を除き、
午後10時から午前5時までの間に労働を免除される制度
適用除外労働者
①日々雇用される者
②勤続1年未満の者
③請求にかかる家族の16歳以上の同居の家族が次の(イ)~(ハ)の要件をすべて満たす場合
(イ)深夜において就業していない者(1ヶ月について深夜における就業が3日以下の者を含む)
(ロ)負傷、疾病または精神上・身体上の障害により、保育が困難な状態でない
(ハ)産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内でないか、産後8週間を経過している
④週の所定労働日数が2日以下の労働者
⑤所定労働時間の全部が深夜にある労働者
子の看護休暇
制度概要
小学校就学前の子を養育する労働者が、申し出ることにより、1年に5日まで、病気・けがをした子の看護のために、休暇を取得することができる制度
適用除外労働者
・日々雇用される者
・労使協定により除外される以下の者
①入社6ヶ月未満の労働者
②1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
今日は、まとめですが、
これを見てもなかなかややこしくて理解できないかもしれませんね。
とりあえずは5つの制度があるということを理解していただければ、それで十分です。

Posted by 青い夜 2006年11月01日09:00│Comments(0)
│概要